ライフスタイル
留学生でも治験で大金ゲット?!ニューヨークで治験するならリスクをしっかり理解しよう

ニューヨークって本当に金かかるんです…ニューヨークは学生とかには厳しい町なんです。そんな金欠な時に飛び込んできたのが「治験」という言葉!しかも2週間で4000ドルとか貰えるって…神か!と突っ込もうとしたのですが、治験にもメリットとデメリットがあるので、それを理解しないといけないと思ったので、まとめてみました。
[Google-ad]
ニューヨークで治験ってできるの?

結構ネットサーフィンしてると「高収入!治験に参加を!」って見るけど、治験ってなんだろ?と思う方のためにgoogleさんに聞きました。
私たちは、病気になったりけがをすると「くすり」を飲んだり注射したりします。そのひとつの「くすり」が誕生するまでに10年以上もの長い研究開発期間 を必要とします。さらに国から承認を受けなければ医療機関や薬局で取り扱うことができません。国から「くすり」として承認を受けるために、さまざまな試験をくりかえし、効き目の確認と安全性の評価が行われますが、最後の段階で健康な人や患者さんのご協力を得て行われる試験を「治験」といいます。http://www.toyama.med.or.jp/wp/?page_id=1475
つまり、治験ってまだ発売されてない薬を実際に体に入れてみて効果を実験します。
「実験!?」って不安になる人もいますが、今使っている薬も何年か前に誰かが治験をして効果が出たものが販売されているんです。それもそのはず!治験で使われている薬は国際基準にのっとり厚生労働省が定めたGCP(Good Clinical Practice)という機関の基準に従って厳格に審査され、治験で使われる薬も各医療機関毎に治験審査委員会(IRB)に審査が入り、許可がおりた薬しか使わないので、危険性は極めて低いです。
また、治験は仕事やアルバイトではなく、あくまでボランティアという位置づけで、報酬は治験に対する「負担軽減費」として扱われるため留学生でも参加することが出来ます。
[Google-ad]
ニューヨークで治験をすることのメリットは?デメリットは?

まずはメリットから紹介します。
1:短期間で高額のお金が手に入る
期間と手に入るお金は1つ1つのプログラムで変動がありますが、2週間で3000ドルとかの治験もありますし、期間が長くなればなるだけ、高額のお金が手に入ります。最近見た一番高い治験は1ヶ月で5500ドルでした。
2:普通の検査以上の細かい検査をされる
治験は試験という側面があることもあり、通常の治療より詳しい検査や診察を行います。それにより今まで知らなかった自分自身が持っている病気なども見つかるかもしれないです。
3:治験で使われる薬は安全性が高い
治験で使われる新薬は、非臨床試験を何年も行い、人間に対する安全性、倫理性の両面の審査をクリアしたものしか使わないため、安全性は高いです。
4:社会貢献の一環
先程も紹介した通り全ての薬が治験をクリアして販売されています。つまり、新薬を使うことはこれからの医療に貢献することにもなります。社会貢献が好きな人にはいいかもしれないですね。
治験をすることのデメリットは?
1:副作用が出る可能性あり
どのホームページみて「治験は安全!」と書かれていますが、100%安全ではないです。その証拠に医薬品医療機器総合機構の調査によると日本国内だけでも平生24年では891件の副作用が確認されています。もちろんレベルも軽度な副作用で済む場合もありますし、重度な副作用もあります。日本国内で先程の数字と考えるとアメリカでは…どれだけあるんですかね。楽して金は稼げないってことです。
2:期間中は好き勝手動けないかもしれない
治験の種類によっては運動や食事制限がある場合があります。中には電子機器の持ち込みを禁止する場合もあります。また治験中は何度も検査にもいかないといけないです。
3:危険レベルをあげれば、あげるだけ危険
治験には危険度レベルがあります。このレベルは生物学的同等性試験に基づいて作られており、危険な順番にPhaseⅠ、PhaseⅡ、PhaseⅢになります。レベルが上がれば上がるだけ報酬額は大きくなりますが、危険性は高くなります。
[Google-ad]
色々ニューヨークの治験に調べたからこそ言えること
ニューヨークに留学する留学生って本当にお金に困っています。それは家賃が尋常じゃない値段だったり、物価が高いことが理由だったり、色々理由はありますが、本当にお金がかかる町です。ですが、覚えておいてほしいのが…
健康はお金では買えないです!
先程も話した通り生物学的同等性試験のレベルが低いものは副作用も少なく、弱いのでやってもいいかもしれないですが、PhaseⅠは金額が高い分、リスクも高いです。これだけは忘れないでください。
あくまでこの記事は「治験に行くな!」という記事ではなく、治験の意味を知って欲しいとおもって書きました。ニューヨークの治験を扱ってる機関では日本人スタッフがいるところもありますし、今までも数多くの人が治験を受けています。多くの人が問題なく治験を終えていますが、中には副作用が出てしまった人もいます。
留学生でも簡単に高額なお金が貰えるから軽い気分で行く人もいますが、そんな人ほどリスクを考えていません。ちゃんとリスクも理解した上で治験に行きましょう!
※この記事は2019/02/02に公開した情報になります
※当サイトに掲載された情報については、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。
ご利用等、閲覧者自身のご判断で行なうようお願い致します。
当ウェブサイトに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切責任を負いかねます。
関連記事
記事はありませんでした
僕がこのブログを運営しています!
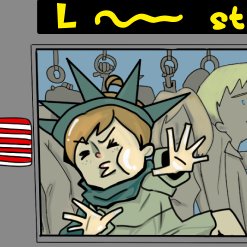
もしニューヨーク旅行の思い出の写真がある方は #私が見たニューヨーク をタグを使ってシェアしてください🌹ニューヨーク好きの人たちがどんな風にニューヨークを楽しんでたのか気になるな... pic.twitter.com/TgEAGDwYuD
— Kei | 小さなニューヨーカー (@smallnycer) May 19, 2020
-

Wassup!NYC!!!ニューヨークヒップホップガイド
ニューヨークで生まれ、発展し続けるHIP HOP!その歴史と文化がまるごとわかる!ジャケット&ミュージックビデオ撮影地・グラフィティの聖地・ショップなどヒップホップにまつわる歴史的現場とアーティストお気に入りの店を網羅してる一冊
-
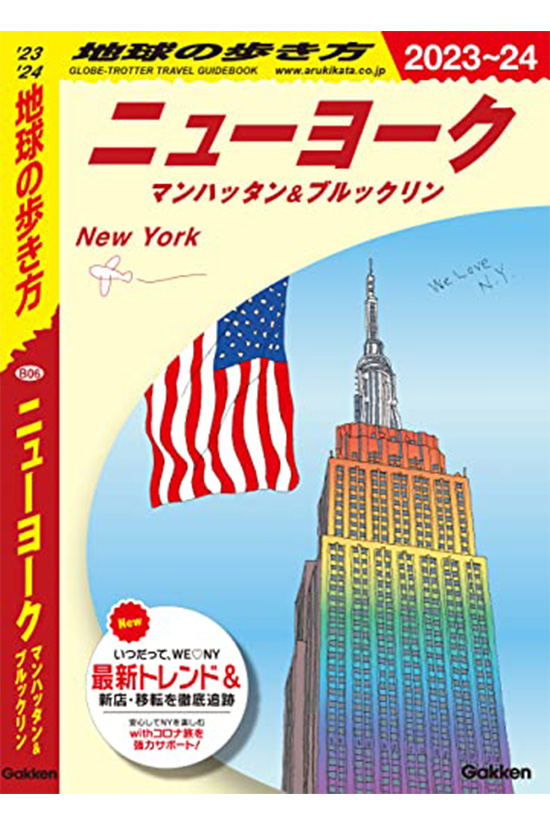
地球の歩き方 ニューヨーク 2023~2024
海外旅行者なら一度は聞いたことのある「地球の歩き方」のニューヨーク版!常に進化する街ニューヨーク、交通もグルメもショップも新顔トレンドがこの一冊にまとまっているのでニューヨーク初旅行者の方におすすめの一冊
-
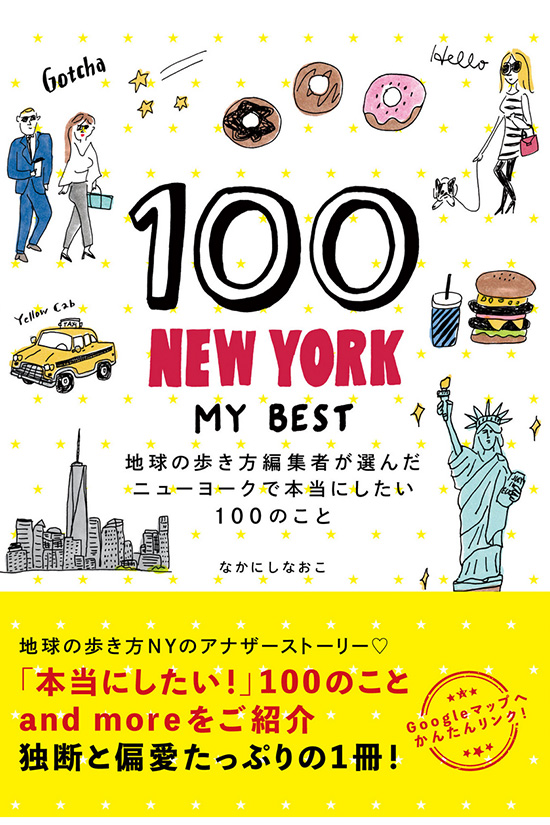
編集者が選んだニューヨークでしたい100のこと
本書は “地球の歩き方のアナザーストーリー”地球の歩き方『ニューヨーク』編の企画・取材・編集を長年担当しているなかにしなおこさんが、ひとりのNYラバーとして選んだ“ニューヨークで本当にしたい100のこと”を紹介している一冊
-
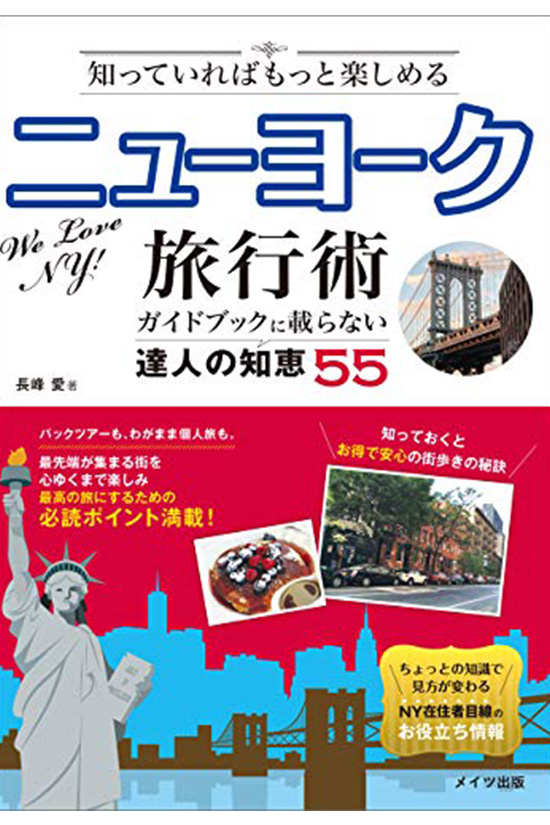
ガイドブックに載らない達人の知恵55
知っておくとお得で安心の街歩きの秘訣を大公開!ニューヨーク在住者目線のお役立ち情報と初めてニューヨークに来る方でも暮らすように旅できるように、知っておきたかった情報をコツとして詰められるだけ詰め込んだ1冊
-
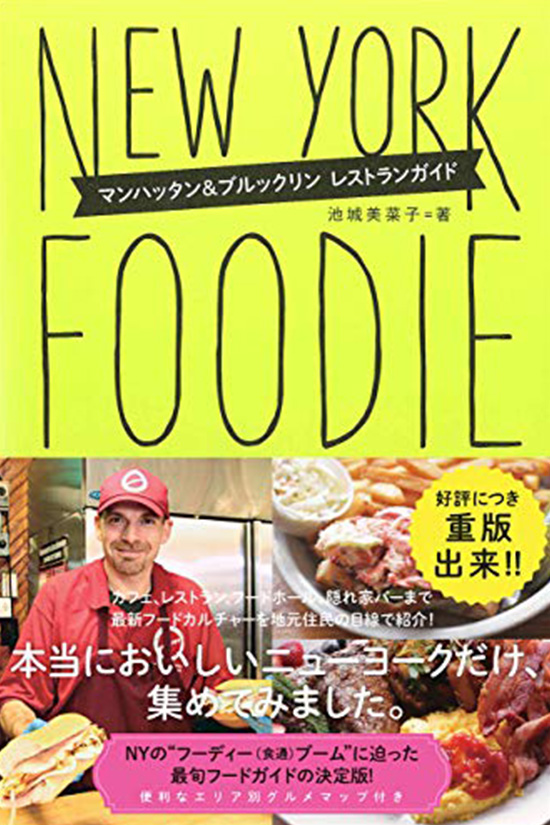
マンハッタン&ブルックリン レストランガイド
本当においしいニューヨークだけ集めた最旬フードガイドの決定版!“フーディー=食通、食い道楽”。「グルメ」みたいに高級志向ではないけれど、とにかくおいしい食べ物、変わった食べ物が大好き!っていう食通の方にぴったりの一冊
-

ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン
ニューヨークの中心マンハッタン地区にありセントラルパークの近く、近代美術館の向かいに位置するスタイリッシュなホテル。セントラルパークも歩いて行ける距離にあるのでニューヨーカーの真似をして朝の散歩をしてみてはいかがですか?
-

ニューヨーク・マリオット・マーキス
タイムズスクエアを象徴するホテルで、観光スポットが充実したロ―ケーションは観光にもビジネスにも超便利!マンハッタンの360度の絶景を望む回転レストラン"THE VIEW"お客様の目の前でアニメーションを活用したユニークで五感を刺激する個性豊かな料理を楽しむことができます。
-

ハイアット グランドセントラル
ハイアット グランドセントラル ニューヨークは映画の文体でも度々使われるグランドセントラル駅に直結した唯一のホテルです。マンハッタンのミッドタウン、42丁目という立地は最高で「ブライアントパーク」や「エンパイヤステイトビルディング」など観光名所へのアクセスも良いホテルです。
-

ザ バウリー ホテル
ザ バウリー ホテルは、ロウアー・イーストサイドとイースト・ヴィレッジが交わる場所に位置しています。レトロな雰囲気が特徴的なホテルで、洋館をイメージさせます。歴史ある建物が好きな人には、たまらないホテル。また24時間対応のコンシェルジュサービスやレンタル自転車を提供しています。
-
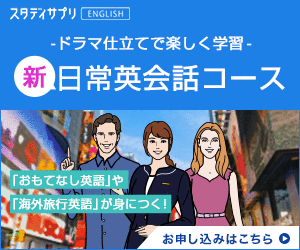
-
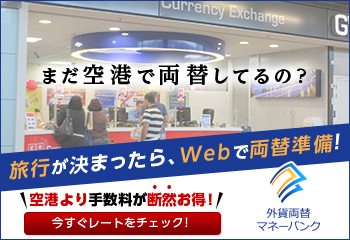
-

必須アイテム!海外WiFiレンタルのグローバルWiFi
「Wifi天国」と言われてるけど無料Wifiの数は多くないし、無料Wifiはハッキングなどのトラブルの元!Wifiレンタルして行きましょう
-

-

もう1年前になるけどめっちゃ好きです#私が見たニューヨーク pic.twitter.com/PYfYPO1Hjl
— N Y P H (@nyph89) May 21, 2020
やっぱりこの街が好き#私が見たニューヨーク pic.twitter.com/Hxlyi7w1pf
— Yukinori Hasumi (@833__3) May 21, 2020
あと100回行きたいTimes Square
— ebi_times/Travel Photographer (@ebi_times) May 21, 2020
#私が見たニューヨーク pic.twitter.com/rFmxqWJoHy
もう5年もたつのかー。何度でも行きたいNY。 #私が見たニューヨーク pic.twitter.com/USnb9tXg4W
— USA (@nimoom0730) June 16, 2021
いつかまた旅に出るその日まで
— 𝙖 𝙨 𝙝 𝙤 𝙠 𝙖 𝙝 🏳️🌈 (@ashokah_) May 21, 2020
#私が見たニューヨーク pic.twitter.com/DncNsxoKF1
2泊4日で行ったけど、全然足りなかった…!!!1番弾丸旅行で行ったことを後悔した都市。
— しん|トラベルコンテンツメーカーNext 🇦🇿🇦🇲🇬🇪🇶🇦 (@worldtips0106) September 7, 2021
あと50回くらいは行きたい🙃
#私が見たニューヨーク pic.twitter.com/AY1rvnLd0Z




















